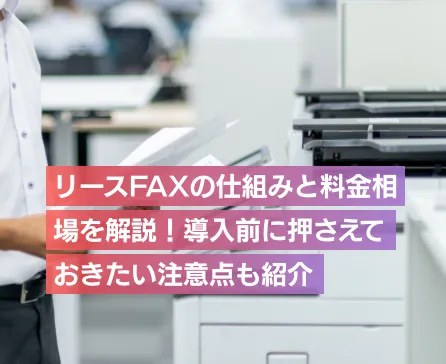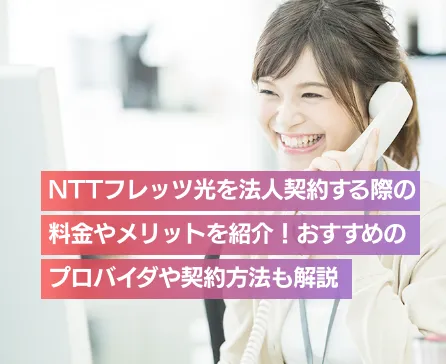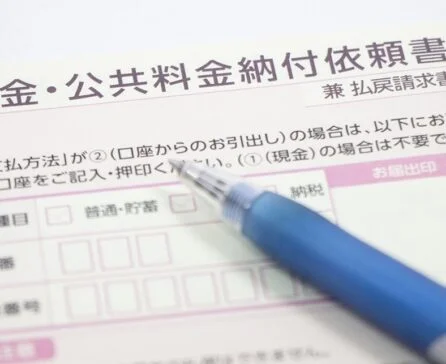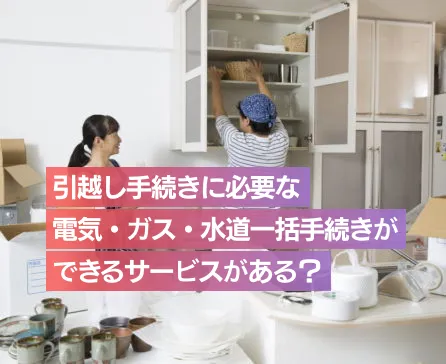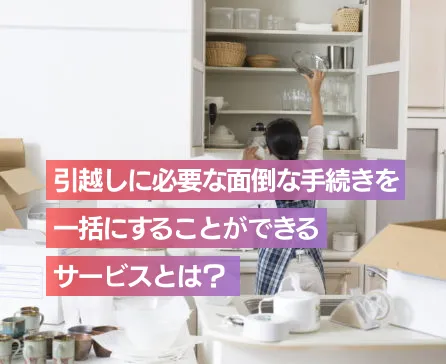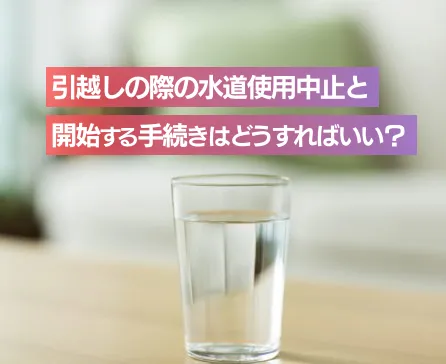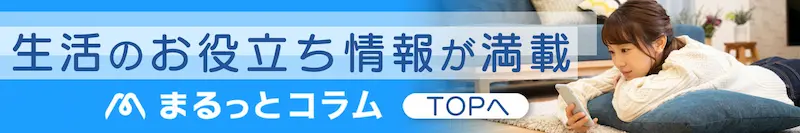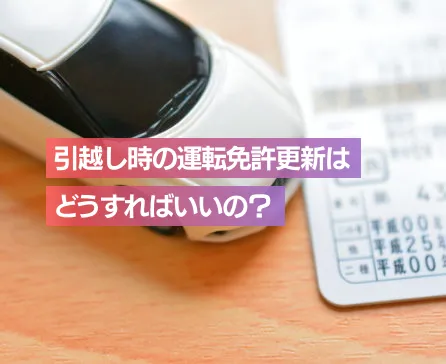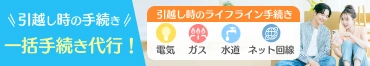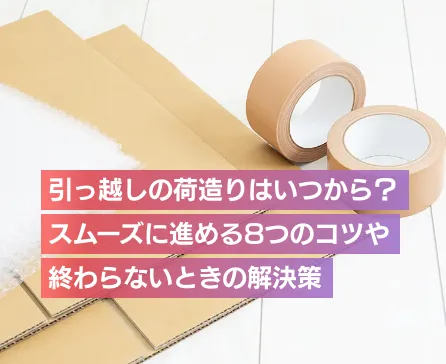
引っ越しの荷造りはいつから?スムーズに進める8つのコツや終わらなかったときの解決策
最終更新日:
引っ越しの荷造りはいつから始めるべきか、どうすればスムーズに進められるか、慣れない作業で迷っていませんか?
荷造り中はどのようなトラブルが起きるのかわからないため、余裕を持つことが大切です。1週間〜1ヶ月前から始めると不測の事態にも対応しやすくなります。
本記事では、荷造りを始めるタイミングやスムーズに進めるコツについて紹介します。作業開始前に準備するものや当日までに終わらないときの解決策も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
なお、荷造りに集中したい方には、ライフラインの手続きを一括で依頼できるサービスの利用がおすすめです。電気やガス、水道、インターネット回線の手続きが無料で行えます。
引っ越しの荷造りはいつから始めればいい?

引っ越し時の荷造りを始めるタイミングは、以下の目安を参考にするのがおすすめです。
- 単身者:1〜3週間前
- 家族:1ヶ月前
引っ越しの2〜3日前から着手した場合、予期せぬ出来事に対応できなくなります。家族の急な体調不良や梱包資材が不足する可能性も考えられるため、余裕を持つことが大切です。
また、不用品を処分する際に、自治体の回収日などを考慮する必要もあります。少しでも運ぶ荷物を減らしたい方は、早めに取り掛かりましょう。
引っ越しの荷造り前に準備しておくもの

荷造りを始める前に、必要な道具や梱包資材を揃えましょう。準備するべきものを紹介します。
荷造り・荷解きに必要な道具
荷造り・荷解きに必要な道具は以下のとおりです。
- 軍手
- カッター・はさみ
- ガムテープ
- セロハンテープ・ビニールテープ
- 油性ペン
- ビニール袋
- 工具 など
いずれもホームセンターや100円均一ショップで購入できるものです。
事前に必要な道具を揃えておくことで、効率よく荷造りを進められます。
梱包資材
荷造りに必要な梱包資材として、以下のようなものを準備しましょう。
- ダンボール
- 布団袋
- ハンガーボックス
- ジップロック
- 緩衝材 など
ダンボールは、業者から無料でもらえる分だけでは足りない可能性があります(一部の業者では有料)。
足りない場合は、自分で購入したり、スーパーなどで無料でもらったりしましょう。サイズが異なるものを用意すると便利です。
布団袋やハンガーボックスは、業者が貸し出してくれる場合があります。事前に確認しておきましょう。
緩衝材は、運搬時に荷物がぶつかる衝撃から保護する役割があります。大切な物を傷つけないために必要です。
具体的には、以下のようなものを緩衝材として利用すると良いでしょう。
- 気泡緩衝材
- ハンディラップ
- 発泡ポリチレンシート
- 新聞紙
- タオル など
引っ越しの荷造りをスムーズに進める8つのコツ

引っ越し時の荷造りをスムーズに進めるには、以下8つのコツがあります。
- 家の中をグループ分けする
- 新居で使う家具を決める
- 使用頻度が低いものを先に梱包する
- 不用品を処分して荷物の量を減らす
- 家電製品を運搬する際の注意点を確認する
- 持てる重さで荷物をまとめる
- 食器や調理器具は緩衝材を使う
- 当日まで使うものはダンボールを分ける
それぞれ確認し、効率よく荷造りを行うためにお役立てください。
1.家の中をグループ分けする
家の中をグループに分けてから、エリアごとに荷造りをしていくと効率的です。リビング・キッチン・洋室1・洋室2・洗面所・玄関のように、グループ分けをしてから取り掛かりましょう。
ダンボールには新居のどの部屋に収納するのかを書いておくと、荷解きがスムーズになります。
異なるエリアの荷物を同じダンボールに詰めると、荷解きの際に部屋を行ったり来たりすることになり、円滑に進められません。
2.新居で使う家具を決める
新居で使う家具を決め、不要なものは早めに処分しましょう。今ある家具をチェックし、新居に搬入できるサイズであるか確認することが大切です。
特に大型ソファやベッドは、解体しないと搬出・積載ができない場合があります。自分で解体するか、事前に業者へ依頼するなどの対応が必要です。
なお、タンスに通帳や印鑑、有価証券といった貴重品が入っていると、引っ越し業者は運べません。貴重品はひとつにまとめて自分で持っていきましょう。
3.使用頻度が低いものを先に梱包する
使用頻度が低い以下のようなものを先に梱包しましょう。
- シーズンオフの洋服
- 来客用の食器
- アルバム・DVD・レコード・本
- 季節装飾品 など
早めに梱包を進めることで、引っ越し直前に焦りながら作業することを防げます。
4.不用品を処分して荷物の量を減らす
不用品を処分して、荷造り・荷解きを楽にしましょう。ごみの回収日は決まっているため、自治体のスケジュールを把握しておくことが大切です。
また、フリマやリサイクルショップで売却したり、知人・友人に譲渡したりすることで処分する方法もあります。
引っ越しギリギリになって不用品を処分しようとすると、業者に依頼するなどの対応が必要になります。焦って必要なものまで処分してしまう可能性もあるため、早めに分別をしながら荷造りを進めるのがおすすめです。
5.家電製品を運搬する際の注意点を確認する
以下の家電製品は、運搬する際に注意が必要です。
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- キッチン家電
- エアコン
- テレビ・DVDデッキ
- 洗濯機
家電製品ごとに運搬時の注意点が異なるため、やっておくべきことを事前に確認しましょう。
例えば冷蔵庫と洗濯機は、引っ越し前に水抜きが必要です。取扱説明書の手順に沿って行い、水気を取りましょう。
また、エアコンは冷媒ガスの回収が必要なので、専門業者を手配して取り外します。引っ越し業者や専門業者に依頼しましょう。
そのほかの家電製品は、コンセントを抜いて汚れを綺麗に掃除しておきます。梱包は引っ越し業者に任せると安心です。
6.持てる重さで荷物をまとめる
荷物を運びやすいように、軽いものは大きい箱、重いものは小さい箱にまとめましょう。
重いものを入れすぎると、底が抜けてしまう可能性があります。さまざまなサイズのダンボールを用意して重さに合わせて梱包しましょう。
なお、重いものは下に詰め、軽いものは上に入れると荷物の破損を防げます。
7.食器や調理道具は緩衝材を使う
割れ物である食器やかさばる調理器具は、新聞紙や気泡緩衝材で包みましょう。
食器はひとつずつ緩衝材で包み、床と垂直になるように立てて梱包すると、破損のリスクが軽減できます。
包丁などの刃物は厚紙を刃の部分に巻き、ガムテープで固定すると安全です。
8.当日まで使うものはダンボールを分ける
引っ越しの当日まで使うものはダンボールを分けておき、すぐにわかる状態にしておくと見失いません。新居でもすぐに使うことができます。
例えば、以下のようなものは分けておくと良いでしょう。
- ティッシュ・トイレットペーパー
- タオル類
- 洗面具
- パソコンなどの精密機器
- 荷解きに使う道具
- 掃除道具
- 使い捨ての食器 など
カーテンや翌日の着替えなども分けておくと、引っ越し直後に困りません。
なお、パソコンやプリンタなどの精密機器は、振動や衝撃で破損しやすくなります。梱包・運搬は引っ越し業者にお任せするのがおすすめです。
引っ越しの荷造りが終わらないときの解決策

引っ越し業者と依頼者が交わす運送条件には「当日までに依頼人が荷造りを終えていること」が義務付けられています。
追加料金を支払って作業員に梱包の手伝いを依頼することも可能ですが、予定作業時間内に終わらないと判断された場合は引っ越しが延期になる恐れがあります。
当日までに荷造りが終わりそうにないときは以下のことを検討しましょう。
- 宅急便で荷物を送る
- 自力で荷物を運ぶ
- 代行業者を利用する
解決策として紹介しますが、できる限りこの状態にならないように荷造りを進めてください。
宅急便で荷物を送る
間に合わなかった荷物が少ない場合は、あとから宅急便などで配送できます。
ただし、梱包・発送の準備のために、引っ越し後、旧居に戻ることになるのがデメリットです。遠距離の場合は、負担が大きくなるためおすすめできません。
自力で荷物を運ぶ
大型の家具や家電を引っ越し業者に任せて、残りの荷物はマイカーやレンタカーを使って自分で運ぶのもひとつの方法です。
ただし、荷物が多い場合は積載量が大きいレンタカーを用意する必要があります。
例えば、全国展開をしている「ニッポンレンタカー」の場合、ミニバン・ワンボックスワゴンを1日レンタルすると17,000~27,000円程度かかります。トラックの場合は大型になるほど高くなり、9,000~26,000円程度です。(レンタル料金:ミニバン・ワンボックス>バン・トラック)
運搬を友人に手伝ってもらう場合は3,000〜5,000円ほどの謝礼金が相場とされており、かかった時間に見合う金額を用意すると良いでしょう。
代行業者を利用する
間に合わないとわかった時点で、荷造り代行サービスや家事代行サービスに荷造りを依頼するのもおすすめです。
ただし、現金や通帳などの貴重品類、危険物の梱包ができないといった規則を定めている場合もあるため、事前に対応範囲を確認しましょう。
引っ越しの荷造りに関するよくある質問
引っ越しの荷造りに関するよくある質問は以下の3つです。
- 引越しの荷造りは何日くらいかかる?
- ダンボールに荷物を入れるときの詰め方のコツは?
- 洋服の荷造りをするときのコツは?
それぞれ解説します。
引越しの荷造りは何日くらいかかる?
荷物の量や人数によっても異なりますが、7〜14日程度かかります。
荷造りにかかる平均所要日数は以下の通りです。
- 単身者:1〜3週間程度
- 家族:1ヶ月程度
不測の事態が起こる可能性もあるため、余裕をもって始めることが大切です。
ダンボールに荷物を入れるときの詰め方のコツは?
荷物の破損を防ぐために、重いものは下、軽いものは上に詰めましょう。ダンボールの中身を新居の部屋ごとに分けると、荷解きが楽になります。
また、持ち運べる重さとサイズで荷物を詰めることで、底抜けを防げます。
洋服の荷造りをするときのコツは?
引っ越し業者から借りられるなら、ハンガーボックスを使うのがおすすめです。シワや型崩れを防げます。
洋服が大量にある場合は、衣類の型崩れを気にしないなら、圧縮袋を使って小さく梱包しましょう。袋の中の空気をすべて抜かず、少し残しておくと衣類への負担を減らせます。
なお、収納ケースに保管しているものはそのままでも運べます。高価なものや下着類は紙袋やほかの衣類で目隠しをして、予期せぬトラブルを防ぎましょう。
ライフラインの引っ越し準備も忘れずに
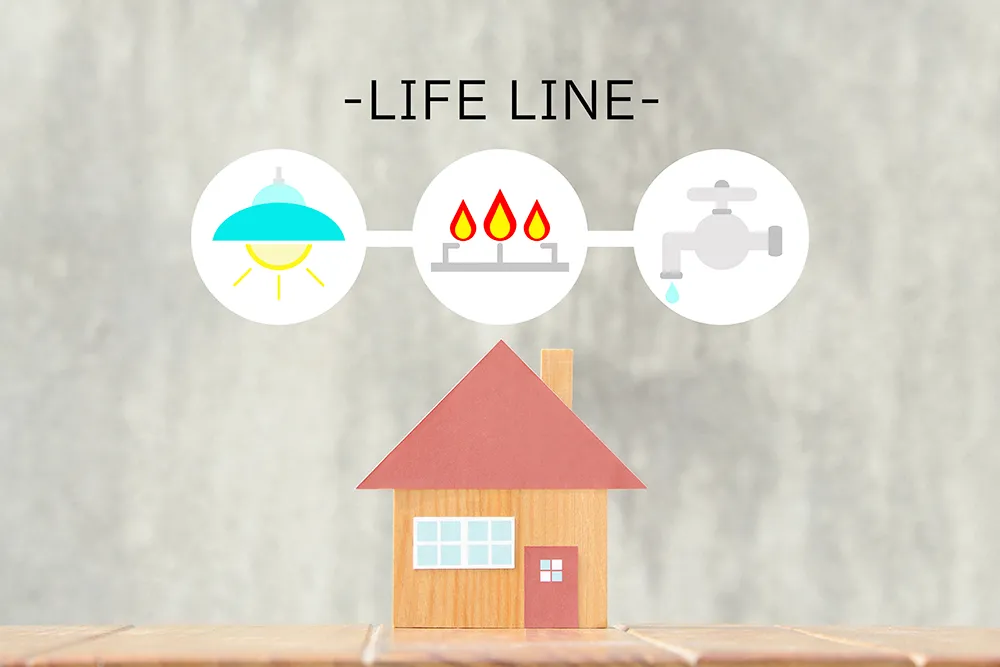
荷造りは家の中をグループ分けし、不用品を処分しながら進めることで効率的に進められます。
引っ越し当日までに荷造りを終えないと、引っ越し業者と交わす契約に違反することになるため、余裕をもって2週間〜1ヶ月前から始めましょう。間に合わない場合は、この記事で紹介した解決策を試してみてください。
なお、引っ越し時は電気やガス、水道、インターネット回線の変更手続きが必要です。荷造りだけでなく、ライフラインの手続きも引っ越しの1~2週間前を目安に行いましょう。
少しでも面倒な手続きを減らして荷造りの時間を増やしたい方には、ライフラインの手続きを代行してくれる「ライフライン一括引越し代行」の利用がおすすめです。
無料で利用できるので、引っ越し費用が増える心配がありません。引っ越し先で最適なプランを紹介してもらえるのもメリットです。
時間がない方は、ライフラインの引っ越しをプロに任せて、その分引っ越しの荷造りに時間をかけましょう。
この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。運営や方針の詳細はコンテンツポリシーを参照ください。
記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら