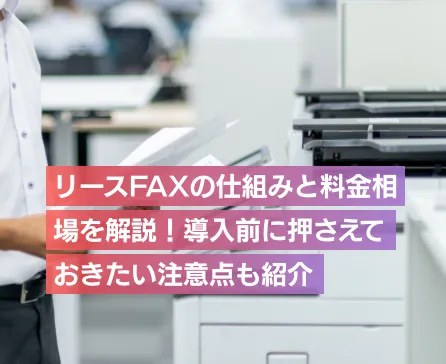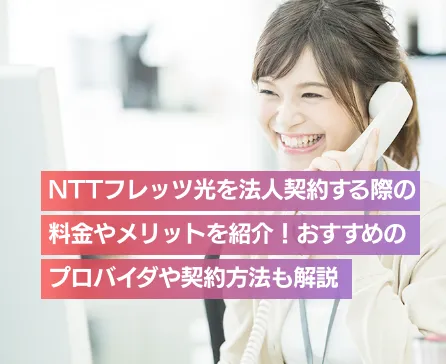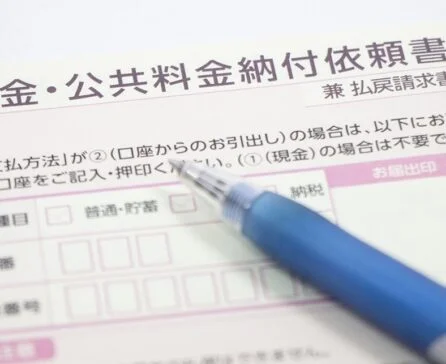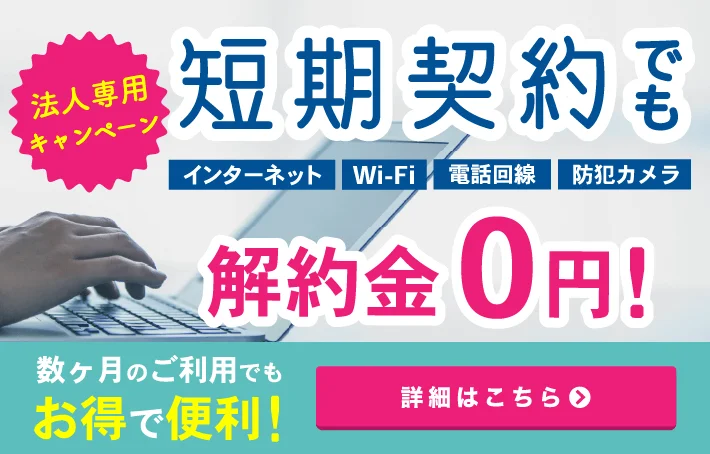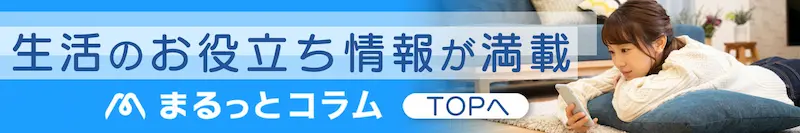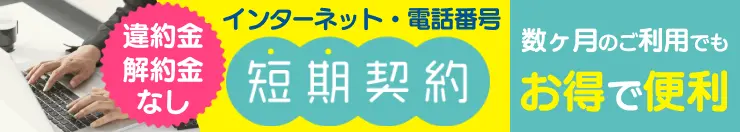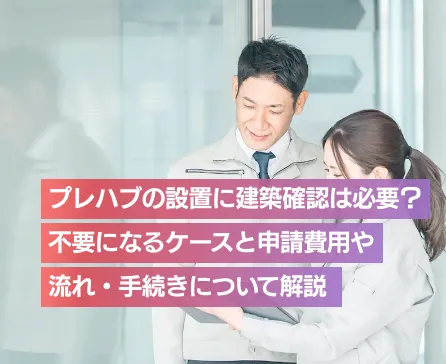
プレハブの設置に建築確認は必要?不要になるケースと申請費用や流れ・手続きについて解説
最終更新日:
プレハブを設置する際に「建築確認が必要かどうか」で迷うことはありませんか?
実は、条件によっては建築確認が不要になる場合もあります。
本記事では、建築確認が不要なケースや、必要な場合の手続きの流れ、申請にかかる費用について詳しく解説します。プレハブをスムーズに設置するために、ぜひ参考にしてください。
なお、建設現場などでプレハブの設置に伴い、インターネットや電話を使いたい方には、NTTの「フレッツ光」がおすすめです。通常期間外の解約は違約金が発生しますが、以下の窓口からの申し込みなら違約金0円で光回線を短期利用できます。
NTTの工事は予約制なので、お急ぎの方はこちらの窓口にご相談ください。
プレハブの設置では建築確認が不要な場合がある

建築基準法では、プレハブも「建築物」として扱われるため、原則として建築確認申請が必要です。建築確認とは、建物を建築する前に、その計画が法的基準を満たしているかを行政機関や指定確認検査機関が審査する制度です。
ただし、特定の条件を満たす場合に限り、建築確認が不要となるケースもあります。例えば、一定の規模以下の建築物や特定の地域に設置する場合などが該当します。適用条件を理解し、適切に対応しましょう。
プレハブ利用時に建築確認が不要な5つのケース

プレハブを設置する際、原則として建築確認申請が必要ですが、一定の条件を満たせば不要になる場合があります。
- 建築基準法の「建築物」に該当しない
- 都市計画区域外での設置
- 防火地域・準防火地域外
- 床面積10㎡以下の場合
- 一部の仮設建築物
建築確認が不要となる主なケースを見ていきましょう。
建築基準法の「建築物」に該当しない
プレハブが建築基準法で定める「建築物」に当てはまらない場合、建築確認申請は不要です。具体的には、以下のような条件が該当します。
- 小規模な物置や倉庫:
奥行きが1m以内、または高さが1.4m以下のものは、建築物として扱われない。
- 移動可能な設備:
地面に固定されず、自由に移動できるコンテナや収納設備などは、建築基準法上の建築物とみなされない。
例えば、外部から荷物の出し入れはできるものの、人が内部に立ち入らない施設は、貯蔵槽のような設備として扱われるため、建築物には該当しません。これは、建築基準法第2条第1号で定められた「貯蔵槽に類する施設」に分類されるためです。
都市計画区域外での設置
プレハブを設置する際、都市計画区域外であれば建築確認申請は不要です。
都市計画区域外とは、都市の開発や整備の対象とされていない地域を指します。この区域は、都道府県知事や国土交通大臣によって指定されます。
都市計画区域外であれば、ユニットハウスなども含め、建築確認の手続きを行わずに設置可能です。ただし、地域ごとの独自の規制が存在する場合もあるため、事前に自治体のルールを確認しておきましょう。
防火地域・準防火地域外
防火地域や準防火地域に指定されていない場所では、プレハブの設置にあたって建築確認が不要となることがあります。防火地域・準防火地域とは、火災の延焼を防ぐために指定された地域で、建築物の構造や使用材料に制限が設けられます。
指定地域では火災リスクを抑えるために厳しい規制が適用されますが、該当しない地域では一定の条件を満たすことで建築確認申請を省略できる場合があります。
床面積10㎡以下の場合
床面積が10㎡以下のプレハブは、建築確認申請が不要となる場合があります。これは、小規模な物置や作業小屋などに適用されるからです。
ただし、防火地域や準防火地域ではこの条件が適用されず、一部分でもこれらの地域に該当する場合は、建築確認申請が必要となるため注意が必要です。
一部の仮設建築物
特定の仮設建築物は、条件を満たせば建築確認が不要となることがあります。
仮設建築物とは、建築基準法第85条第6項及び7項(仮設建築物の許可)により安全性や防火性、衛生面で問題がないと認められた場合に、一定期間のみ設置が許可される建築物を指します。
例えば、工事現場に設置される仮設事務所や資材置き場は、基準を満たすことで申請が不要です。また、災害時の仮設住宅やイベント用のパビリオンなども、状況によっては建築確認申請が免除される場合があります。
プレハブで建築確認が必要な場合の流れと手続き

プレハブ建築において建築確認が必要な場合の基本的な流れと手続きは以下の通りです。
- 建築確認申請(着工前)の準備
- 特定行政庁等で書類確認
- 建築確認済証の交付後の対応
- 工事着工と完了検査の申請(完成後)
- 検査済証の交付手続き
建築確認の手続きを適切に進めることで、法令違反を防げます。順番に見ていきましょう。
建築確認申請(着工前)の準備
プレハブ建築を行う際は、まず建築確認申請をする必要があります。
この申請は、建物が建築基準法や地域の条例に適合しているかを審査するための重要な手続きです。申請時には、以下の書類を準備しましょう。
- 建築確認申請書:設計図や建築計画の詳細を記載した書類。
- 建築計画概要書:敷地面積、建物の構造や用途など、基本情報をまとめた書類。
- 委任状:施工業者が代理で申請を行う場合に必要。
- 審査受付票:申請受付時に使用される書類。
- 建築工事届:建築主や工事期間、建物の用途などを記載する申請書。
適切な書類を準備し、事前に内容を確認してから申請すると、スムーズに審査を進められます。
特定行政庁等で書類確認
申請書類を準備した後は、特定行政庁または指定確認検査機関に提出します。提出後、書類の審査が行われ、必要に応じて補正や追加説明を求められることがあります。
法令上、指定確認検査機関での審査期間には特に定めがありません。建築確認申請は工事前に行う必要があり、通常、申請後に審査が完了するまでには約1〜2か月かかります。
建築確認済証の交付後の対応
建築確認が承認されると、確認済証が交付されます。この証明書は工事を開始するために必要であり、受け取るまで工事を始めることはできません。通常、申請から約35日以内に交付されます。
工事着工と完了検査の申請(完成後)
工事が完了した後は、完了検査の申請を行います。完了検査は、建物が設計図どおりに建築されているかを確認するために実施されます。
建築確認申請の内容に基づいて工事が行われたかどうかを、実際の建物を確認しながら判断するものです。工事完了後、4日以内に申請する必要があります。
検査済証の交付手続き
完了検査が問題なく終了すると、検査済証が交付されます。完了検査の申請後、工事内容に不備がなければ、検査済証が発行されます。
この証明書は、建物を使用するために欠かせない書類です。また、一度失効すると再発行ができないため、慎重に管理する必要があります。
プレハブの建築確認申請にかかる費用

プレハブを建築する際には、建築基準法に基づき、建築確認申請が必要です。この申請には、行政手数料や設計士への依頼費用など、さまざまな費用が発生します。
| 項目 | 費用の目安 |
| 確認申請手数料 | 各自治体によるが、床面積が30㎡以内の建物の場合、約25,000円程度が一般的 |
| 現場調査費用 | 一級建築士による現場調査や図面作成にかかる諸経費が含まれ、合計で約50~70万円程度 |
| 中間検査・完了検査手数料 | 中間検査や完了検査が必要な場合、追加で数万円の手数料が発生 |
費用は建物の規模や自治体の規定、依頼する専門家によって異なりますが、一般的な相場を知っておくことで、スムーズに準備を進められます。ここでは、プレハブの建築確認申請にかかる主な費用について詳しく見ていきましょう。
申請手続きにかかる費用相場
建築確認申請に必要な費用は、地域や建物の種類、面積によって異なります。一般的な相場は以下の通りです。
- 簡易建物(床面積50㎡以下):約55,000円
- 新築4号物件(床面積200㎡未満):1㎡あたり1,320円(最低費用105,600円)
- 木造特殊建築物(床面積200㎡以上):1㎡あたり1,650円(最低費用158,400円)
この費用には、設計図面の作成や申請書類の準備が含まれます。具体的な金額は依頼する業者や自治体の規定によって異なるため、事前に詳細を確認しておきましょう。
行政手数料や専門家への依頼費用
建築確認申請を行う際には、行政に支払う手数料が必要です。手数料は建物の床面積によって異なり、例えば、床面積が100㎡を超える場合、14,000円~19,000円程度が一般的です。
また、申請手続きを専門家に依頼する場合は、設計士や建築士への費用も発生します。
- 設計図面作成費用:依頼内容によって異なりますが、数万円~十数万円程度。
- 申請代行費用:施工業者に依頼する場合、手数料が追加されることがあり、数万円~十数万円程度。
費用を総合的に考慮し、事前に予算を立てることが重要です。特に、自治体ごとに異なる規定や手数料があるため、詳細を確認しておく必要があります。
プレハブの建築確認申請に必要な書類
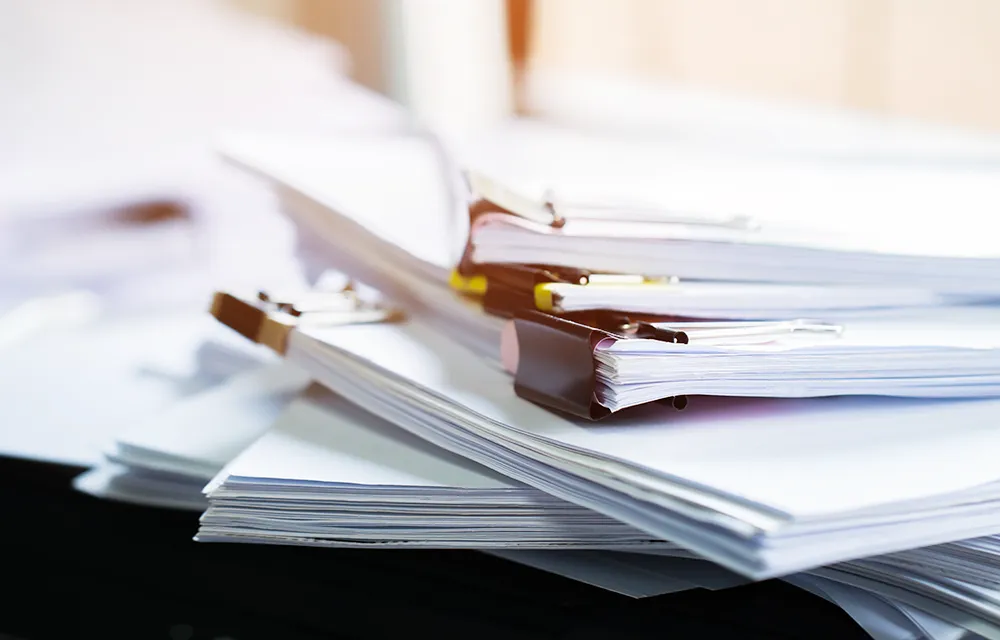
建築確認申請を行う際には、以下の書類を提出する必要があります。
- 確認申請書
- 建築計画概要書
- 配置図
- 平面図
- 公図
- 工事届
- 構造計算書
- 委任状
- その他の関連書類
提出が求められる書類は自治体や建築計画によって異なる場合があるため、事前に必要な書類を確認しておきましょう。
プレハブ設置時の建築確認申請に関する注意点
ここでは、プレハブ設置時の建築確認申請に関する3つの注意点について解説します。
- 申請が漏れると建築基準法違反になる
- 地域によって規制内容が異なる
- 申請には費用と時間がかかる
プレハブを設置する際には、建築確認申請が必要になる場合があります。申請を怠ると建築基準法違反となり、行政からの指導や是正命令を受ける可能性があるため、ポイントを押さえておきましょう。
申請が漏れると建築基準法違反になる
建築確認が必要な場合に申請を行わないと、その建物は違法建築物とみなされます。
建築確認とは、建築基準法に適合しているかを確認する手続きのことで、一般的に10㎡を超えるリフォームや増築を行う際には申請が必要です(一部の建物や地域を除く)。
申請を行わずに建築を進めた場合、法律に適合していないと判断され、行政から是正を求められることがあります。さらに、建物の使用禁止や撤去を命じられることもあり、経済的な損失が発生するだけでなく、周囲の安全にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
地域によって規制内容が異なる
建築確認申請の基準は地域ごとに異なるため、事前に確認することが不可欠です。特に、都市計画区域内では厳しい規制が設けられているケースが多く、建物の用途や床面積によって申請の必要性が変わる場合があります。
例えば、防火地域や準防火地域では、建物の規模にかかわらず建築確認が求められるケースもあります。そのため、設置を予定している場所の規制内容を十分に調べ、適切な手続きを進めることが重要です。
申請には費用と時間がかかる
建築確認申請を行う際には、申請手数料が発生し、確認済証の交付までには一定の時間を要します。一般的に、申請から交付までは2週間~1ヶ月程かかることが多いですが、書類に不備がある場合や追加の審査が必要な場合は、それ以上の期間を要するケースもあります。
また、申請にかかる手数料は建物の規模や地域によって異なり、数万円~数十万円かかることが一般的です。手数料の支払いは、申請時に指定された期日までに現金で行う必要があるため、余裕を持って準備しておきましょう。
プレハブで建築申請以外に確認・準備する項目

プレハブを設置する際には、建築申請だけでなく、内部の設備やライフラインの準備も必要です。具体的な内容については、「現場事務所に必要なものがまるわかり!忘れがちな注意点も解説」をご確認ください。
また、現場で短期間のみインターネットを利用する場合は、違約金の発生しない契約が可能な窓口を選ぶと安心です。以下の窓口から申し込むと、違約金なしでインターネット回線を短期契約できます。
詳細が気になる方は、ぜひ以下のリンクからご相談ください。
プレハブの建築確認についてよくある質問

プレハブの設置や建築確認申請についてよくある質問は、以下の3つです。
- プレハブ店舗の建築確認はどうすればいい?
- コンテナハウスの建築確認は不要?
- ミニハウスの建築確認はどうすればいい?
よくある疑問に対する具体的な回答を理解し、スムーズに建築計画を進められるようにしましょう。
プレハブ店舗の建築確認はどうすればいい?
プレハブ店舗を設置する際には、建築確認申請が必要です。特に、都市計画区域内での設置や延べ面積が10㎡を超える場合は、必ず申請を行わなければなりません。
通常、申請手続きは施工業者が代行しますが、建築士に依頼して必要書類を作成することも可能です。提出が求められる書類には、配置図、平面図、立面図などが含まれます。
コンテナハウスの建築確認は不要?
コンテナハウスを設置する際は、一般的に建築確認申請が必要です。コンテナハウスは建築基準法上の「建築物」とみなされるため、固定して使用する場合は、建築基準法に基づいた確認申請が求められます。
ただし、都市計画区域外であり、かつ床面積が10㎡未満の場合は、一定の条件を満たせば建築確認が不要となるケースもあります。具体的な条件は地域によって異なるため、事前に地元の自治体へ確認しておきましょう。
ミニハウスの建築確認はどうすればいい?
ミニハウスを設置する場合も、建築確認申請が必要です。特に、都市計画区域内に設置する場合や、延べ面積が10㎡を超える場合は、申請を行わなければなりません。
また、防火地域や準防火地域に設置する際は、特別な防火基準を満たす必要があります。申請手続きは、施工業者や建築士に依頼するのが一般的ですが、ミニハウスの規模や用途、地域の条例によって要件が異なるため、具体的な内容については事前に自治体や建設課へ問い合わせて確認することが大切です。
プレハブは建築確認が不要な場合も!インターネット・電話の準備も忘れずに!

プレハブの設置において、建築確認が不要なケースを理解することで、手続きを簡略化しスムーズに設置を進めることが可能です。都市計画区域外や床面積10㎡以下、防火地域外など、条件を満たせば建築確認なしで設置できる場合があります。
一方で、建築確認が必要なケースでは、申請の流れや費用を把握し、事前に準備を整えることが重要です。設置後の業務を円滑に進めるために、インターネットや電話の環境も事前に整えておきましょう。
なお、建設現場などでプレハブの設置に伴い、インターネットや電話を使いたい方には、NTTの「フレッツ光」がおすすめです。通常期間外の解約は違約金が発生しますが、以下の窓口からの申し込みなら違約金0円で光回線を短期利用できます。
NTTの工事は予約制なので、お急ぎの方はこちらの窓口にご相談ください。
この記事は執筆された時点での情報を元に記載されております。文書・写真・イラスト・リンク等の情報については、慎重に管理しておりますが、閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。運営や方針の詳細はコンテンツポリシーを参照ください。
記載内容や権利(写真・イラスト)に関するお問合せ等はこちら
あなたにオススメ

工事現場でのインターネット・固定電話利用に最適な方法は?

現場事務所でインターネット(Wi-Fi)!高速通信する最適な方法
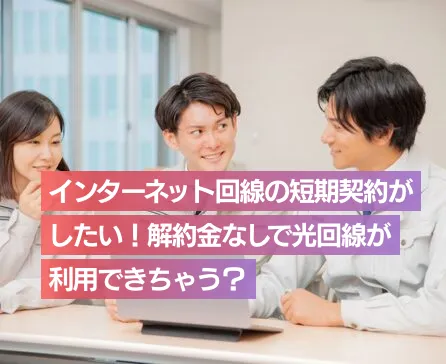
インターネット回線の短期契約がしたい!解約金なしで光回線が利用できちゃう?

選挙事務所開設に必要な物は?電話やインターネットを短期契約する方法!

プレハブ事務所のレンタル費用はいくら?工事現場・仮設事務所のネット回線はどうする?

固定回線(光回線)の短期契約はできる?違約金なしで解約できる方法を紹介!

光回線の1年契約(半年契約)は可能?解約時の違約金を気にせずNTTのフレッツ光が使える!

現場事務所でWi-Fiを使う一番いい方法をご紹介!容量・通信速度を気にせず使用可能!
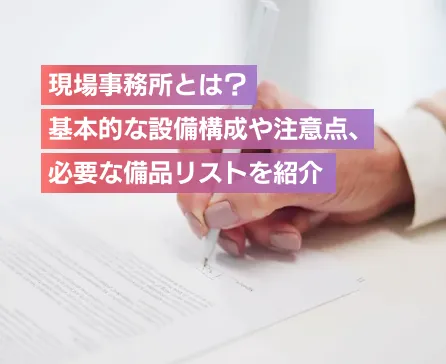
現場事務所とは?基本的な設備構成や注意点、必要な備品リストを紹介

【工事現場】仮設トイレのレンタル費用の目安は?設置の流れや注意点もご紹介
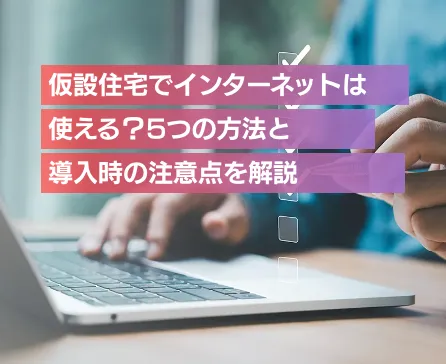
仮設住宅でインターネットは使える?5つの方法と導入時の注意点を解説